
このページの監修医師

このページの監修医師

骨盤臓器脱 (子宮脱・性器脱) の手術、リスクやデメリットはある?
目次
骨盤臓器脱(子宮脱・膀胱瘤など)とは、膣のヘルニアなどとも呼ばれ、子宮・膀胱・尿道・小腸・直腸などが、女性器(膣)に下垂し膣外に出てきてしまう病気です。別名「性器脱」、「膣脱」ともいわれ、古には「なすび」と云われた疾患です。
骨盤内臓器(子宮、膀胱、直腸)は、筋肉、靭帯、筋膜で構成された骨盤底筋によって支えられています。骨盤臓器脱は、それらの組織が弱くなり、膣から骨盤内臓器が1つまたは複数出てきてしまう病気です。
出てくる臓器によって、子宮脱・膀胱瘤・尿道瘤・小腸瘤・直腸瘤と呼ばれていて骨盤臓器脱(子宮脱・膀胱瘤など)とはその総称です。それらを総称して骨盤臓器脱といいます。
海外ではPelvic Organ Prolapse (POP)の名称を用いられ、日本でも骨盤臓器脱(子宮脱・膀胱瘤など)という名称が使われるようになりました。
最初は膣から何かが落ちてくるだけですが、進行すると排尿困難や排便困難、性機能障害なども起こるようになります。痛みや出血のため、歩行困難になるなど、著しくQOL(生活の質)を低下させます。
また、恥ずかしさから病院にも行けず、家族や知人にも言えず、人知れず悩んでしまう病気でもあります。
骨盤臓器脱の根治治療は手術になります。手術には様々な方法があります。患者様の年齢や健康状態、症状や程度、パートナーとの性生活の有無、ご本人の希望なども考慮し、医師が判断します。
持病や合併症などある人は手術が出来ないこともあり、その場合は保存的治療法が有効が選択されます。しかし、近隣に病院がない場合、あるいは専門医が近くにいないなどの理由で、受診できない方も多いのが現状です。
まずは自分でできる保存的治療法を取り入れてみることが、症状を進行させず、日ごろの生活を難なく送る近道です。
| 術式 | 概要 | メリット | デメリット | 手術時間 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子宮摘出術 | 下がってきた子宮を摘出する方法 | 子宮がんや子宮筋腫のリスクはなくなる | 妊娠できなくなる | 282,100円 | |
| 膣縫縮術 | 弱っている膣の壁(筋膜)を縫い縮める方法 | 簡便に行える | 痛んだ組織で形成しているため、再発のリスクがある | 腟壁形成手術:78,800円
腟断端挙上術(腟式、腹式):291,900円 |
|
| 従来法 (上記2つを同時に行う) |
子宮摘出後に膣壁を縫い縮める方法 (婦人科で最も多く行われている) |
婦人科で最も多く行われていて、低侵襲である | 痛んだ組織で形成しているため、再発のリスクがある | ||
| 経膣メッシュ手術(TVM) | 弱っている膣の壁をシート状のメッシュで補強する方法 (授産の可能性がある場合は行わない) |
・経腟的に手術をするため開腹せず患者の負担が少ない ・再発のリスクが低い |
日本では安全に行われているが、合併症や後遺症が問題となり、現在海外では禁止されている(注) | 30分~2時間30分 | 膀胱脱手術:
【1】メッシュを使用するもの:308,800円 【2】その他のもの:232,600円 |
| 膣の閉鎖 | 膣の前と後ろの壁を縫い合わせて、臓器が落ちないようにする方法 腟閉鎖術は性機能温存を希望されない高齢者に行う |
・短時間で手術が可能 | 性交ができなくなる | 腟閉鎖術:
【1】中央腟閉鎖術(子宮全脱):74,100円 【2】その他:25,800円 |
|
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC) | おなかに数カ所の小さな穴を開ける腹腔鏡下にて、骨盤臓器脱によって下垂した膣を、メッシュを用いて仙骨へ固定する方法 (授産の可能性のある若い人にも行える) |
・入院期間が短い ・術後の痛みが軽い ・癒着が少ない ・再発率が最も低い |
・子宮摘出を行う ・手術費用が高い ・実施施設が少ない 長時間の低頭位(頭を低く保つこと)のため、緑内障や動脈瘤がある方は受けられません。 |
60分~4時間 | |
| ロボット支援下仙骨膣固定術 | ロボット(ダヴィンチという機械)を用いて行う仙骨膣固定術。 本来はミリ単位での難易度の高い手術だが、高性能かつ鮮明な手術支援ロボットを使って行うことで、安全かつ効率的な手術が可能。 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)のメリットに加えて ・身体への負担が少ない |
・子宮摘出を行う ・手術費用が高い ・実施施設が少ない 長時間の低頭位(頭を低く保つこと)のため、緑内障や動脈瘤がある方は受けられません。 |
2~3時間 |
(注)2019年4月16日 FDAは骨盤臓器脱に対する経腟メッシュ手術に使用する外科用メッシュの2社3製品に対し製造と販売を中止
※右から左にスクロールいただくとさらに情報をご覧いただけます。
子宮摘出手術:282,100円
膣縫縮術 腟壁形成手術:78,800円
膣縫縮術 腟断端挙上術(腟式、腹式):291,900円
経膣メッシュ手術(TVM):膀胱脱手術【1】メッシュを使用するもの:308,800円
経膣メッシュ手術(TVM):膀胱脱手術【2】その他のもの:232,600円
膣の閉鎖:閉鎖術【1】中央腟閉鎖術(子宮全脱):74,100円
膣の閉鎖:腟閉鎖術【2】その他:25,800円
臓器脱に対する手術にはさまざまな選択肢があり、それぞれ手法と目的に応じて異なります。
子宮摘出手術は、重度の症状に対処するための基本的な手術の一つで、膣関連の手術としては、腟壁の形成および腟断端の挙上術が行われることがあります。また、経膣メッシュ手術は膀胱脱の治療に広く用いられ、メッシュの使用方法によって手術の内容が異なります。
これらの手術は、患者それぞれの症状や必要性に基づいて行われるので、事前に十分な情報収集をした上で医師との相談を行うようにしましょう。
手術の選択にあたっては、費用を含め、術後の回復プロセスも含めて事前に総合的な理解をするようにしましょう。
古くから婦人科で行われている手術で、膣から出てきている子宮を摘出し、前と後ろの膣の壁を切り取り、縫い縮める方法です。痛んだ組織を縫い合わせるため、将来的に膣の壁が緩んできて、膀胱や直腸、小腸などが出てきて再発となるケースも高いです。
経腟メッシュ手術(TVM)とは、英語のTenshion-free Vaginal Meshの略で、膣壁にメッシュでテンションが掛からないように、緩んだ筋肉の変わりに補強してあげようという手術です。
この手術は、2000年にフランスのコッソン先生によって開発され、2004年に竹山先生や島田先生によって初めて行われました。その後、日本でも普及するようになりました。
しかし、メッシュ露出、感染、びらん、疼痛、再発などの問題もあり、FDA(米国医薬食品局)は、2008年と2011年に2度の注意喚起を出し、2019年4月には2社3製品について、完全撤退するよう命じました。これを受け、現在はアメリカを始め殆どの国で禁止となっています。
本邦では、日本製のORIHIMEというメッシュで、現在も安全に手術が行われています。
腹腔鏡下仙骨膣固定術とは、腹腔鏡下でメッシュを用い、子宮頚部と仙骨(お尻の骨)に固定するという手術です。Laparoscopic Sacrocolpopexyという英語の略で、LSCとも呼ばれています。
多くの病院がTVMから撤退して行く中、LSCは現在ではスタンダードとなりつつあります。
再発については少ないとされていますが、文献により様々です。合併症については、感染などが挙げられます。
LSCは、お腹から膣を持ち上げるため、膣の奥行も確保でき、膣にメッシュを入れないことから、性交時の違和感も少なく性機能が温存できます。若い人でも受けることができる手術です。
しかし、一部のエキスパートの医師は2時間以内で手術が可能ですが、通常は3時間(6時間かかる場合もある)程度かかるため、術中は身体への負担も少なくはありません。
上述の仙骨膣固定術を、手術用ロボットを用いて行う手術です。2020年4月より、ダヴィンチ<da Vinci>サージカルシステムの骨盤臓器脱への保険収載が行われ、保険適用範囲内での手術が可能になりました。
高性能な手術用ロボットは高精細で操作性もよく、腹腔鏡下で行うよりも手術を効率的にすすめることができます。そのため、患者さんの身体への負担も軽くなることが特徴です。
高齢で寝たきりや、ご主人がいないなどの理由で性交渉のない場合は、鉛筆が一本入るくらいの隙間を残し、膣を閉鎖します。しかし、会陰部全体が下がってきて、臓器は出ないまでも下垂感を感じたりと、再発する方も少なくはありません。基本的には健常者には行われない手術です。

手術には様々な方法があります。それぞれについては、メリットやデメリットがあります。再発や合併症などのリスクも考慮し、その方に一番合った手術方法が選択されます。
また、心臓病や糖尿病などの持病のため、手術を受けられない方も多くいらっしゃいます。その場合は、リングペッサリーの装着や、フェミクッション(サポート下着)などの保存的治療法が選択されます。
子宮脱の始まりは、子宮が膣内に下垂することから始まります。この頃は、下腹部に違和感を感じたり、下腹部痛として症状が現れる場合もあります。医療機関を受診しても、この時点では手術とはなりません。
ただ、痛みや違和感のため、生活に支障が出ている場合は、フェミクッションを利用される事をお薦めいたします。フェミクッションを使用することにより、弱ってしまった骨盤底筋をしっかりサポートし、痛みや違和感の緩和、子宮脱症状の悪化を防ぐことができます。
骨盤臓器脱を放置すると、血液の流れが悪くなり、うっ血や血流障害が起きてしまいます。そのため、なんらかの方法で治療が必要となります。しかし、手術を直ぐに選択できない場合もあるので、その場合は、保存的治療法が有効です。
リングペッサリーと言って、輪っか状のものを膣内にいれ、臓器が下がってこないようにする方法で、最も良く行われています。簡便ですが、定期的に交換するため、受診が必要です。
また、違和感、出血、びらん、肉芽、感染などの理由で外す場合も多くあります。階段を上る時や、腹圧がかかった瞬間に落ちやすくなるといったこともあります。
最近では、自己脱着を推奨している医療機関も増えてきました。膣に触れることができない、指先に力が入らないなどの理由で、自己脱着を行えない方も少なくはありません。
フェミクッションは患者さんご自身で簡単に脱着でき、簡便にお使いいただける治療具です。骨盤臓器脱の辛い症状から、とにかく早く解放されたいという方にお薦めの方法です。
専門医を探しているがどこを受診していいかわからない、手術をしたいが持病でできない、リングペッサリーで不具合があるなど、様々な理由で、痛みや出血などの辛い症状を日々感じている方も多くいらっしゃいます。
フェミクッションは、手術とは異なり根治治療ではありませんが、履けば直ぐに違和感から解放され、通常の日常生活を取り戻していただけます。
また、リングペッサリーのように体内に挿入するものではなく、腹圧の高い日中のみ使用し、夜は必要ありません。洗って衛生的に使うことができ、感染や合併症など、リスクの心配の少ない治療方法です。
最近では、手術の前後にフェミクッションを使う先生も増えています。術前に使用することにより、リングペッサリーで痛んだ膣の状態を良くします。術後に使用することにより、再発予防となります。
| フェミクッション | 骨盤ベルト | |
|---|---|---|
| 圧迫の方向 | ||
| 圧迫の方向 | 下から上への圧迫(吊り上げ) | 横方向の圧迫 |
| 圧迫する臓器 | ||
| 圧迫する臓器 | 脱出した骨盤臓器 | 骨盤の骨 |
| 圧迫するメカニズム | ||
| 圧迫するメカニズム |
①膣内までクッションで優しく持ち上げる ②縦ベルトによる吊り上げ 
|
骨盤臓器に対する圧迫効果なし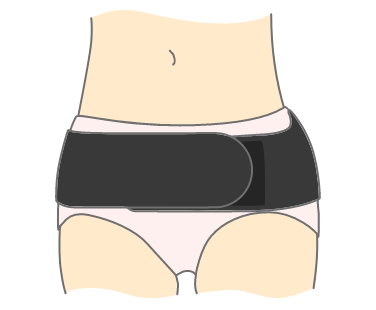
|
| 骨盤臓器脱に対する 効果 |
||
| 骨盤臓器脱に対する 効果 |
有用 | 無効(骨や靭帯の可動性は出産直後でも1cm未満のため) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |
| 骨盤臓器脱による 排尿障害に対する効果 |
||
| 骨盤臓器脱による 排尿障害に対する効果 |
有用 | 無効(上記理由による) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |
| 骨盤臓器脱による 排便障害に対する効果 |
||
| 骨盤臓器脱による 排便障害に対する効果 |
有用 | 無効(上記理由による) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |
| 国の認定 | ||
| 国の認定 | 医療機器 | 雑品 ※効能効果を謳うことこはできない 骨盤臓器脱や尿失禁の効果があると言って 売られている商品があるのでご注意ください |
フェミクッションは、既に十数年の実績があります。この間、全国の多くの先生からお問合せをいただきました。実際にフェミクッションを診療に使われている医療機関、外来にサンプルが置いてある医療機関など様々ですが、これまでに情報提供させていただいております医療機関をご紹介しております。(先生の移動など当時と状況が変わっている場合もありますがご了承ください)
https://urogyne.jp/medical_institution/
・Samuelson et coll, Am J Obsted Gynecol 1999
・Paulo Palma et al. Femicushion™: a new pessary generation – pilot study for safety and efficacy. Pelviperineology 2016; 35: 44-47
・加藤久美子,鈴木省治 骨盤臓器脱に対するサポート下着の使用経験 臨床泌尿器科 第64巻 第10号 別冊 2010年9月20日発行
・加藤久美子,鈴木省治, 鈴木晶貴ほか:女性骨盤底疾患の保存的治療:サポート下着(フェミクッション). 日本女性骨盤底医学会誌9:30-36, 2012
・加藤久美子,鈴木省治, 鈴木弘一, 服部良平:排尿障害プラクティスの保存的療法:日本女性骨盤底医学会誌2013年6月10日発行 第21巻2号
・FDA takes action to protect women’s health, orders manufacturers of surgical mesh intended for transvaginal repair of pelvic organ prolapse to stop selling all devices
・FDA Orders Mesh Manufacturers to Stop Selling Devices for Transvaginal Repair of Pelvic Organ Prolapse

永尾 光一 先生
東邦大学 医学部教授(泌尿器科学講座)
東邦大学医療センター大森病院 リプロダクションセンター
東邦大学医療センター大森病院 尿路再建(泌尿器科・形成外科)センター長
昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。
所属医療機関

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役
三井 桂子
株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役。日本における女性疾患についての認知や理解度の低さに危機感をおぼえ、医療機器開発に着手。子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱の治療に用いる「フェミクッション」を開発し、三井メディカルジャパンを通じて発売。
スターターキット ライトネット購入限定

まずは試してみたい
という⽅に!
セット内容
・サポーター1枚(ミディベージュサポーター)
・クッション 3個(S・M・L各サイズ1個)
・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)
・洗浄栓
※スターターキット ライトをご選択の方はミディベージュサポーターのみとなります。
スターターキット

普段の⽣活でしっかり
使いたい⽅に!
セット内容
・サポーター1枚(次の項目で種類・サイズを選択ください)
・クッション 6個(S・M・L各サイズ2個)
・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)
・洗浄栓
※コットンの特注サイズは現在在庫切れです。